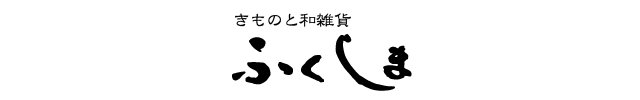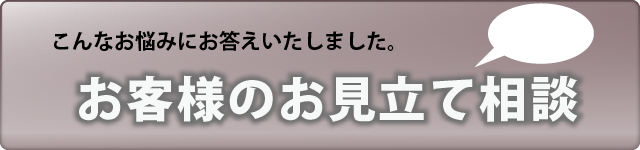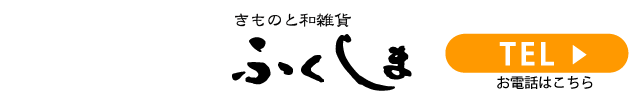長くお付き合いをさせていただいているお寺の住職さんが店にお越しになられていまして、私にこのような話をしてくださいました。
長引くコロナ禍で経営に関わる人達は何処も大変なご苦労があるが、うまい話に乗ってはダメよ!
これまでに沢山の経営者のご家族と触れてきているが、経営者の軸がブレはじめると、後に取り返しのできない出来事が起きるものよ・・・。
具体的な話を例にとって、因果応報(いんがおうほう)という言葉を使って話してくれていましたが、その意味が良く分からなくて調べてみると、
幸せや不幸という結果に至った「原因」があるという意味で、「過去に悪いことをしていれば悪いことが自分に戻ってくる」「過去に良いことをしていれば良いことが自分に戻ってくる」といった表現として使用されいる仏教の教えを表す言葉だそうです。
確かに、経営者として迷い道に入り込んでしまうと、信念を持ち続けることが出来なくなっていて、甘い香りがする方向へ向ってしう。
このような話は身の回りにゴロゴロあって、危険な社会になっていることは確かなことです。
そのことを私に伝えたかったのかもしれません。
住職さんは私に、無理をしないでコツコツと続けていくことが大切で、家族が仲良く元気の暮らせているのなら、それがなによりも幸せなことなのよ・・・。
経営者として、一人の人間として、当たり前のことを言われているのに、心に響くところがありました。
気にかけてくださるお客様が身近にいてくれるって有り難いことです。
感謝しないといけませんね。
話題は替りますが、地元の呉服店が次から次へと廃業して行っていることもあるのか、着物のお洗濯やシミ落とし、寸法直しや子供の着物の縫い上げなど、新しいお客様が毎日のようにいらっしゃいます。
地域の人達のお役に立てていると思うと、嬉しく思うところがあります。

お客様が持ち込まれた縫い直しの訪問着
昨日も新しいお客様から訪問着の寸法直しの相談があり承らせていただいた。
腕首までの長さを裄(ゆき)といいますが、その裄の長さを約4.5㎝出して、着物の丈もお客様の身長に合わせて欲しいとの相談です。
訪問着が古典柄でいい着物だったので、「洗い張り」をしてから縫い直すことをお勧めさせていただきました。
洗い張りとは、仕上がっている着物を反物になるように縫い合わせてから、水洗いで着物の汚れ落とした後に、針の付いた竹ひごや張り板にピンと張り、糊付けしてシワを伸ばしながら乾かしていく方法です。
洗い張りをすると縫った跡が、ある程度消えるので、寸法を大きくされる方には必要な仕事かと思っております。
洗い張りをすると、凹凸のない着物生地になり仕立て師さんが縫いやすく、部分的に直すのと違って、綺麗な仕立て直しとなります。
着物に優しい仕立て直し方かと思っていまして、思い入れのある着物や、高価な着物の縫い直しは、洗い張りから始めることをお勧めさせていただきます。
持ち込まれたお客様には、長襦袢と共に洗い張りをしてから仕立て直しをすることをお勧めすると、快く承諾してくださって、明日、京都の専門業者に出したいと思っているところです。
そんな折り、夏紬の衿の汚れ落としの相談にいらしたお客様が、クリーニング店との違いを尋ねられましてね~
クリーニング店の仕事がどのようなものなのか詳しくは知らないのでなんとも言えませんが、お客様と接点を持つ人が、着物に詳しいのがこの店かと思っていて、お客様の着物を見て、気づいたお直し点をいくつか申し上げると、納得された様子で、汚れ落としを承ることとなりました。
お直し法もいろいろあって専門知識が必要となりますが、経験を積み重ねるといろんなことが分かってきて、お客様のお役に立てているのではないかと思っております。
訪問着をお預かりしたお客様には、画像の提供をいただきまして感謝しております。
ありがとうございました。
ではこれにて・・・
お休みなさい。
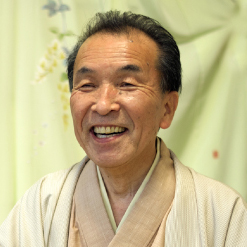
はじめまして。きものふくしま店主福島正弘です。
石川県、金沢市のお隣の白山連峰が見えるところで着物と和雑貨を販売しております。
着物和装に携わって約40年。県内外問わず、全国の着物ファンの方々から様々な相談を受けております。
店主の紹介をさせていただきます。
昭和30年、福井県に生まれる。 昭和48年に京都の染屋で修業を積み、その後昭和51年に石川県の呉服店へ勤務。着物の世界に触れながら「いつか自分のお店を持ちたい」という夢を抱き続け、昭和61年に 「きものふくしま」 を創業しました。
創業当初は無店舗での経営からスタートし、10年目に念願の店舗をオープン。以来、着物ファンを増やすことを使命に、お客様とのつながりを大切にしてきました。
情報発信への取り組み 25年前から四季を楽しむ情報紙『あ・うん』を毎月発行。 20年前からは毎日ブログを更新し続け、新しいお客様との出会いを広げています。
技術と経験 約40年にわたり呉服業界で培った確かなコーディネート力には自信があります。お客様一人ひとりの個性を引き出し、着物をより身近に楽しんでいただけるよう努めています。
「きものふくしま」は、着物を通じて人と人を結び、四季の彩りを楽しむ暮らしを提案し続けています。
法人名: 有限会社きものふくしま
法人番号: 8220002000118
白山市商工会会員
本日までのブログ総数:7,177記事